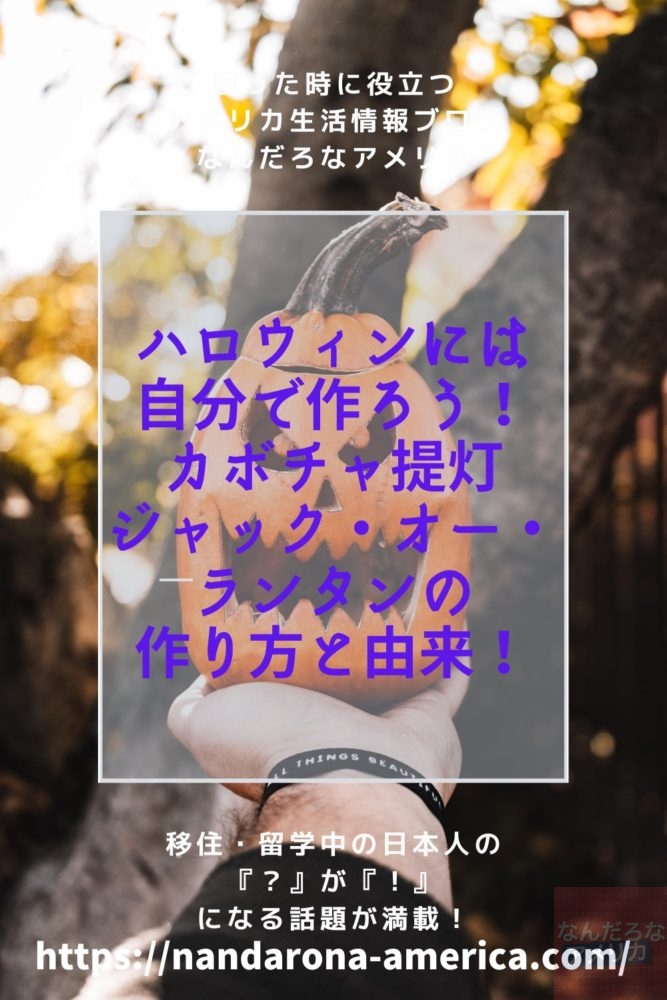北米では秋といえばハロウィン、ハロウィンといえばパンプキンの季節です。
この記事ではハロウィンに欠かせないパンプキンのデコレーション「ジャック・オ・ランタン」(Jack-O’-Lantern)の作り方と、由来についてバッチリ紹介します!
なんだろな☆アメリカがおすすめするアメリカ便利グッズカタログ@アマゾン マガジン風にお楽しみいただけます
Jack-O’-Lanternを作ってみよう!
ジャック・オ・ランタン(Jack-O’-Lantern)とは、ハロウィンの際の風物詩、オレンジ色のパンプキンをくりぬいたり彫刻を施したデコレーションのことですが、アメリカでは子供を中心に、ハロウィン前に必ずと言っていいほど体験する「季節のDIY」です。
今回、娘と作ってみましたので、作り方と由来についてたっぷりご紹介します。
ハロウィン関連の記事は他にもこんなものがあります!
アメリカ生活ールーツを知ったらもっと楽しめる!ハロウィンの起源についてー
アメリカ子育てー学校でHalloweenパレード!学校のイベント内容紹介ー
NJ子育てーパンプキン!Hay Ride! Suydam Farmの魅力7つ!ー
アメリカ映画ーハロウィンといったら絶対欠かせない映画7作品!
アメリカ映画ーハロウィンと言ったら『ホーカス・ポーカス』!魅力6点紹介ー
アメリカ子育てー親必見!ハロウィンのTrick or Treat の安全対策とはー
ハロウィン最恐専門店!アメリカSpirit Halloween大スケールの店内大紹介!【画像注意】
アメリカ生活ーMichaelsはアート&クラフトのお店!賢い割引サービスの使い方も紹介ー
アイルランドがルーツのハロウィン
なので、中にろうそくを灯す「ランタン」(ちょうちん)としての利用に向いてるんですね。
ちなみに、ハロウィンの発祥、アイルランドでは、もともとハロウィンの日に魔除けとして芋やカブをくりぬいてランタンを作っていたそうです。
そう、ハロウィンもジャック・オ・ランタンもアイリッシュに伝わる文化。
元々はアイルランド、スコットランドの方のお祭りだったそうです。
魔よけ、というのは、10月31日が「あの世の霊がこの世にも彷徨う」日なので、邪悪な霊に悪さをされないように、「怖い顔の彫刻を施したランタン」で悪霊退散、そして、お菓子を供えて「これで勘弁!」「こっちには入ってくるな!」としたそうです。
アメリカにアイルランド人が渡ってから、「パンプキン」を使うようになったそうです。
移民がもたらす文化、異国での新たな変化、面白いですね。
ジャック・オ・ランタンは超常現象(?)が元々のアイデア
アイルランドの湿地、沼地の上によく目撃されるwill-o’-the-wispと呼ばれる「火の玉」のような発光現象が別名Jack-O’-Lanternと呼ばれていたことに由来するようです。
片手に中が空洞の(カブでできた)ランタンを持ち、彷徨う男、「ジャック」の民話があるようです。
↑ワシントン・アーヴィングのお墓参りに行ってきましたー!
気味悪い男が夜な夜な片手にランタンを持って彷徨う、というのはワシントン・アーヴィングの小説「スリーピー・ホロウ」の「首なし男」に通ずるものがあります。
ハロウィンの歴史、ぞくっとするイメージはこうやってアメリカの地でも脈々と生きていますねえー。いいですねー。
↑ニューヨークの「スリーピー・ホロウ」(小説の舞台)にHeadless Horsemanの彫刻があるの!
こういう現象は探せば万国共通であるのかもしれないですね。
日本ならば人魂や鬼火といったところでしょうか。
妖怪のような、自然の現象と人々の創造力、恐怖があいまったもののような感じ。発光現象、というのは昔の人はさぞかし怯えたことでしょう。(今もびっくりするだろうけど)
夏休みが終わる9月初旬にもなると、スーパーやお店にこうやって様々なパンプキンが並び始めます。アメリカの四季を感じるこういったイベントっていいですね。
子供がいると、さらに「これは絶対体験させないとかわいそう!」と焦るので、親も無理やり積極的になります。(笑)
パンプキンを見ると秋を感じる
アメリカに住むと、日本と違う年中行事とそれに伴う街の景色の変化に最初の数年は目も心も奪われますが、私は今だにパンプキンの季節になるとときめきます。(笑)
なぜかというと、アメリカの秋は長く美しいから!そして、長く厳しい冬の前に、頑張って満喫しておかなきゃ!と夏の疲れも忘れ、心にエンジンがかかるからです。
日本もそうですが、秋は芸術、読書、食欲、などなど心も体も肥える(笑)季節です。
アメリカでは特に、美しく長く楽しめる紅葉に心奪われ、冬よまだ来ないでー、と日に日に寒くなり、日が短くなる季節に祈るように過ごすのです。
美しくも変化にあふれ、そして体も過ごしやすい季節ですね。
パンプキンにはいろいろあります
さて、「パンプキン」と一言で言っても、サイズ、色、形が様々あり、スーパーにふらっと行くと様々なウリ科の仲間を目にします。
ジャック・オ・ランタンに最も適しているタイプは見てすぐにわかるかと思いますが、大きくて(大、中、小様々あります)最もよく売られているもの。
スーパーの出入り口付近なんかに山積みされています。価格は大きなものなら10ドル前後、小さいものなら$3ー$5程度です。
10月末ギリギリに農場なんかに行くとセールをしていることがあります。
ファーマーズマーケットや農場の直売に行ける方は、そちらもオススメです。
↑これは食べられないけれど、とりあえず飾るタイプ
↑シュガーパンプキンといって、日本の小玉スイカを一回り大きくしたくらいのサイズ。これは中身が甘く、柔らかく、パイの中身として利用します。だいたい値段は$2−5位ですかね。
↑こういった感じのミニパンプキン(Jack-Be-Little) や、グリーンや白の様々なパンプキンは基本的に食用にはせずに、飾って楽しみます。本当に色々な種類、形があって面白い。値段は小さいものなら80セントから1ドル50セントといったところ。
Jack-O-Lanternを作ろう
さて、ジャック・オ・ランタンを作る際に適しているパンプキンは、皆様よくご存知の、大きくてオレンジ色のが適しています。
↑こういった大きいものです。サイズ、形、いろいろありますが、作品のイメージと合わせて選ぶのもいいでしょう。よく比較すると、縦に長いものや横に潰れた感じのものなど、個性があります。
アメリカのパンプキンと日本のかぼちゃは違う!
実際ジャック・オ・ランタンをみてわかったのは、ランタン用の「パンプキン」は日本でいう「かぼちゃ」なのかというと、そうではないことですねー。
ハロウィンの「パンプキン」は日本のかぼちゃとは全く違い、(同じウリ科ですが)中身が空っぽです。はい、驚くほど空っぽです。食べる果肉の部分ががほとんどない!ちょっとびっくり。
もともとどういう意図で栽培していたのか、どうやって食べていたのか興味が湧きます。
なにはともあれ、さあ、ジャック・オ・ランタン、作りましょう!
1 パンプキンを選ぶ
今回、私は娘と初めて一緒にちゃんとランタン作りをするので、近所のパンプキンパッチ(畑)にて二つ購入。大きさ、形ともに似た感じのものを選びました。
大きいんだけど意外と軽い。(まあまあ重いけど)思ったよりは重くはない、という感じです。さすが空っぽ。スイカより軽いですよ。
買う前にどんなパンプキンの顔にするか、どんなテーマ、キャラクターにするかなど考えて、どこを正面にするのが一番見栄えがいいのかなど決めておいた方がいいですねー。
2 道具を揃える
道具の準備ですー。といってもスーパーでセットを買うだけで終わりです。
スーパーなどでこういった(画像が悪くてすいません)Pumpkin Carving (パンプキンを彫る)道具一式が売られています。
小さなノコギリ、大きなノコギリ、プラスチックの針、そして画像に写っていないですが、縁がギザギザしたしゃもじ型のシャベルのような道具、そして説明書のセットで$6でした。
Spirit Halloween などハロウィン専門店に行くとこれでもかというほどツールが売られていますし、スーパーでもたくさん売られています!
こういったセットはあるとないとでは全然作業の能率が違うので、絶対買うのをお勧めします。
また来年も使えますから、いい投資ですよ。
その他道具として、ペン、パンプキンから出たタネを入れておくボウル、果肉を入れておくボウル、ビニールのゴミ袋や捨ててもいい新聞紙(パンプキンの下に敷きます)を適宜用意しました。
さあーどんどん行きます。
3 下書き
付属の説明書によると、かぼちゃの底面を丸くくりぬくと、底面にろうそくや電球などをセットしやすいので良いとのことだったので、今回は言われるがままに底面を切り抜くことにしました。
まず油性ペンでざっくりと丸を描きました。
そして糸鋸でサクサク切っていきます。思ったより柔らかく、糸鋸がすっすっと運んでやりやすかったです。この糸鋸、優れもの!
切り抜いたパンプキン底面はちゃんと取っておきます。捨てませんー。
まずここら辺で10分経過といったところ。
4 中身を取り出す
中身はまあ、ほとんど空なんだけど、繊維と大量のタネがありますので、綺麗に取り出します。
この時重宝するのがギザギザしゃもじ君ですねー。画像だと隠れて見えないけど。
パンプキン内部はすっからかんなんだけど、糸状の繊維と、大量のタネが入っています。
切り口からもかなり水が出てくるのでビニールや新聞紙は引いておかないといかんです!(笑)水分がかなり多いです!
タネは取っておいて、洗って、オーブンで焼いてカリポリ中身を食べるのがハロウィンの風物詩だそうです!(Twitterで教えていただきました。)やってみたところ、旦那が美味しいと頑張って食べていました。
5 中身をこそぐ
タネと繊維を取り終わったら、必要に応じて中の果肉をこそぎます。この時もギザギザしゃもじ君が大活躍します!しゃもじ君は大きいのでこそげる面積が大きく、サッサカできますね。有能!
デザインにもよりますが、表皮を削って、中にライトやキャンドルを入れて照らした時に、厚さで濃淡を出す作品にするなら、中の果肉を少しこそいで、薄めにしておいたら光がより明るく見えて仕上がりが綺麗、ということですねー。
6 下書きをする
作りたいもののデザインによるかと思いますが、今回うちは娘がはまっている「ナイトメア・ビフォー・クリスマス」のジャックとサリーを作りました。
こういうキャラクターものの場合は、実際のイラストを参考に、ペンでパンプキン表面に下書きをしておくと、あとは糸鋸でなぞってくりぬけばいいだけですから、下書きは必須ですねー。
三角や三日月型を組み合わせてシンプルな顔を作るくらいなら、いきなり糸鋸でカットするんでも問題ないと思います。
7 下書き通りにくり抜く
糸鋸が大、小二種類あったおかげで大きな穴も、細かい細工もとても簡単に作ることができました。
何より、パンプキンがシャキシャキ切りやすいので気持ちいいですねー。
出来上がった感じこんな風になりました。(ジャック)
これだけだとインパクトに欠けるので、さらに顔の部分の皮を彫刻刀で削いで、中の白い果肉を出す感じにしました。
8 中にライトかキャンドルを入れて灯す
ハロウィン当日、夜中にキャンドルを灯して外に置いたらこんな感じに。
こっわ!!!!
これは子供達には刺激が強かったかと思いきや、近所の子供達がTrick or Treatに来ると「これ知ってるー」などとかなり評判が良かったです。(有名な映画だからねー。)
ちなみに、パンプキンの中に入れるライトは$3くらいで売っています。
Jack-O’Lanternを作る時の注意
今回実際作ってみて、気づいたことをいくつかまとめます。
- 結構散らかるので新聞紙、大きなゴミ袋を敷くなどが必要。庭など外でできる環境であれば、外で作業したほうが気楽です!
- 糸鋸、尖った道具は小学生に入る前のお子さんは無理です。親御さんがやってね。
- こうやって穴を開けると、外の小動物、虫がたかって食べにきますので、ハロウィンの2、3日前にやるのがいいですね。うちのはアリがすごかったです。
- パンプキンは、外で霜に当たるとすぐ、ぐしゃぐしゃになり始めます。もしハロウィン当日前に夜中氷点下になるようであれば、パンプキンは家の中に入れて置いたほうが長持ちするかと思います。
- お子さんにとっては最高のクラフト!毎年やらせたい!
なんだろなポイント! めんどくさい!と思っても、作ってみると結構簡単! Pumpkin Carvingはとっても楽しいので、ぜひ家族でやってみて!
まとめ
さて、いかがでしたか?ハロウィンの風物詩、Jack-O’-Lanternの由来と実際の作り方を紹介しました!とても簡単なので、今までチャレンジしたことがなかった方も是非今度のハロウィンにはお試しあれ!
それでは、最後まで読んでくださりありがとうございました!またお会いしましょう。
なんだろなアメリカの全記事リストはこちら!